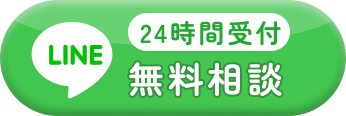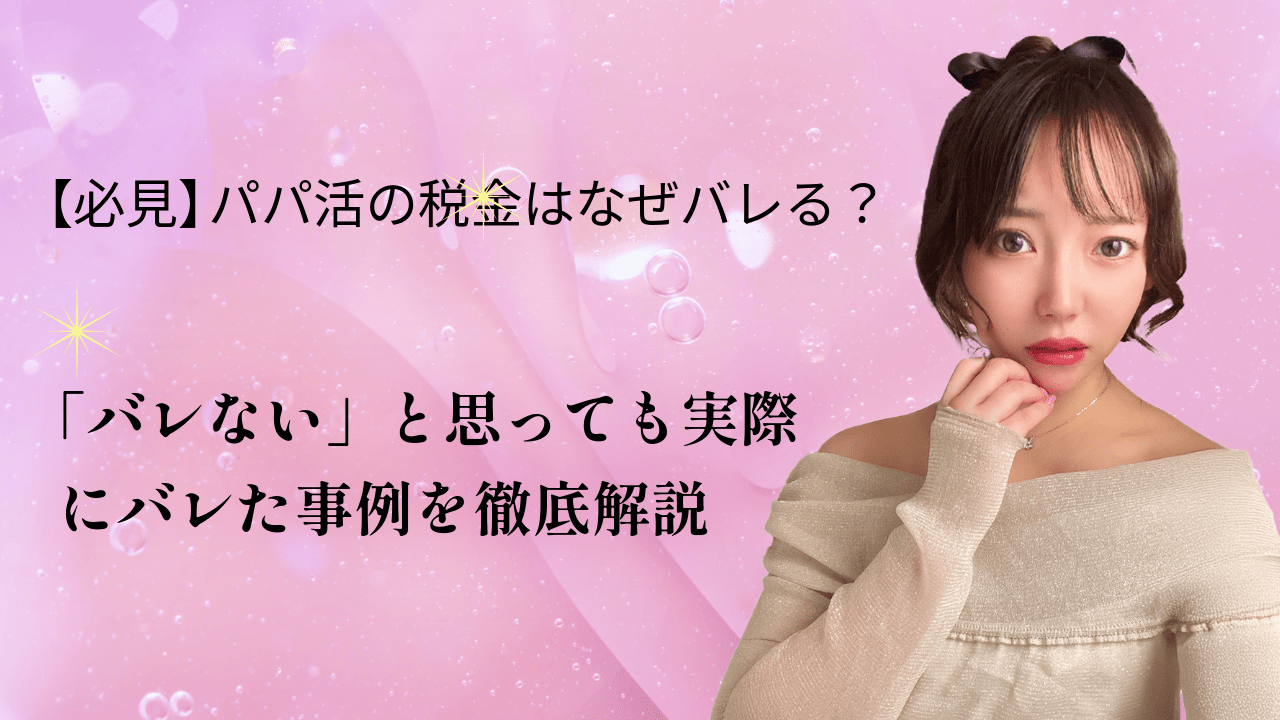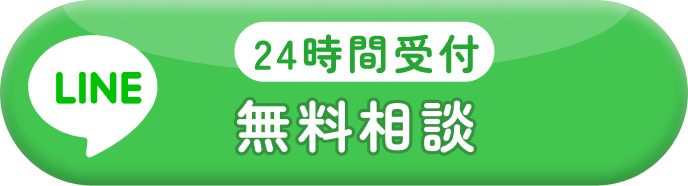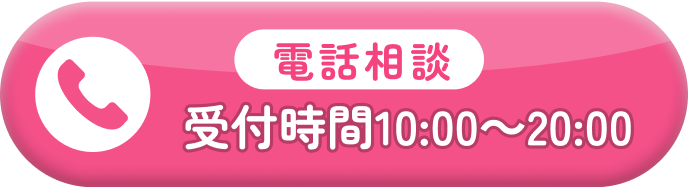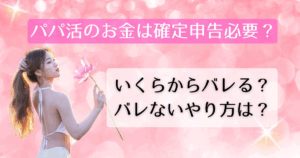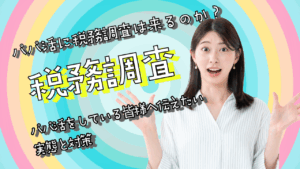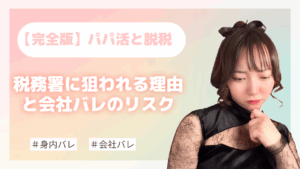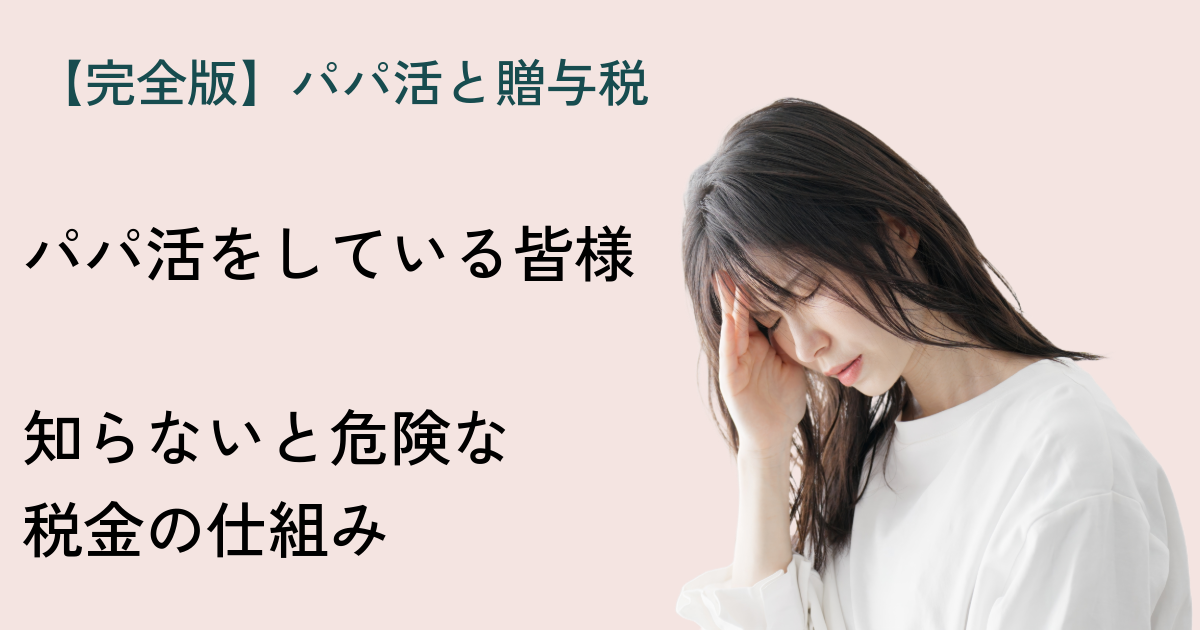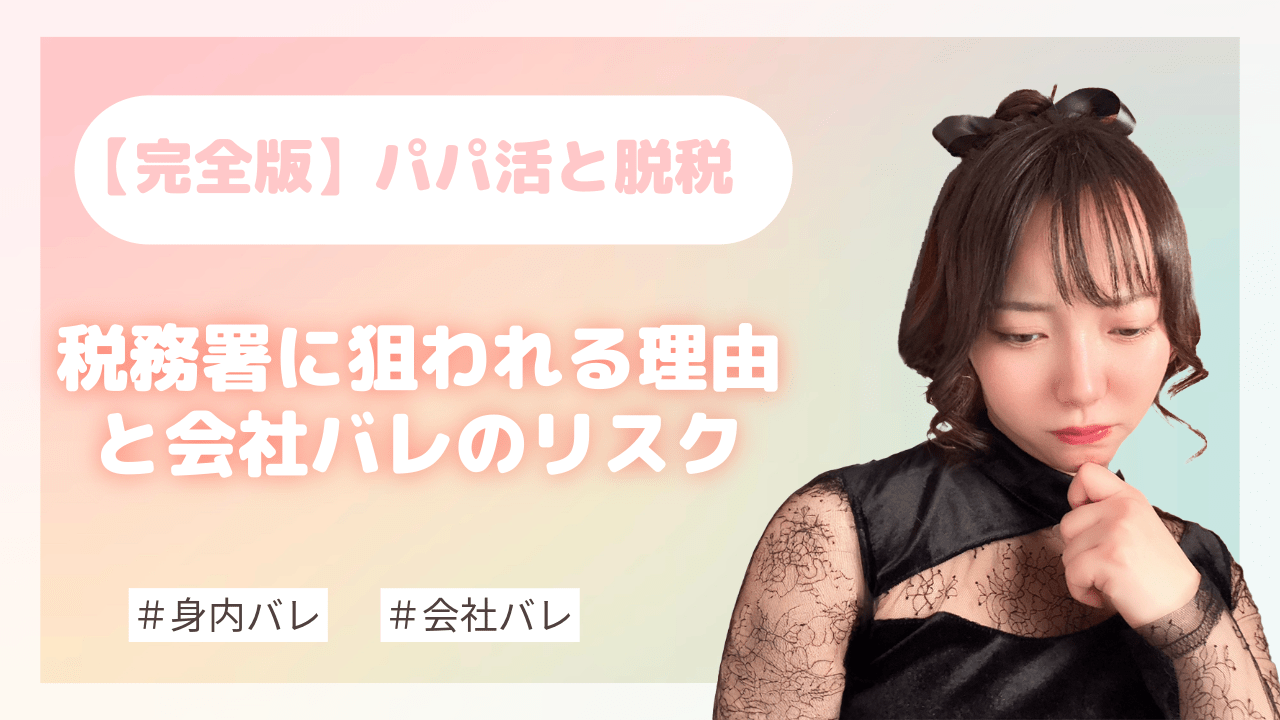実際には税務署は銀行口座やマイナンバー、SNS、住民税通知など多様なルートから収入を把握します。
さらに金融取引やSNSを専門に監視する部署も存在します。
税金がなぜバレるのか、その仕組みとリスク、そして対策を解説します。
この記事を監修した税理士

記事監修者
公認会計士・税理士
内山智絵
※略歴はページ下部に掲載
※本ページの内容は、運営税理士が執筆し、税務の専門家である 内山智絵公認会計士・税理士の監修のもと公開しています。
実際の業務は、私たち「夜TAX 確定申告センター」チームの税理士が対応いたします。
あわせて読みたい
1. 税金がバレる仕組みの全体像
税務署は「本人が申告していない収入」を複数の情報網から突き止めます。
代表的なルートは以下の通りです:
- 銀行口座・送金アプリ
- マイナンバーとの紐付け
- 住民税の通知
- SNSやネット投稿
- 第三者からの通報
これらの情報は個別に集められるだけでなく、税務署内の専門部署がデータを突き合わせることで収入の不一致が浮かび上がります。
2. バレる原因①:銀行口座や送金アプリ
- 振込や入金記録はすべて金融機関に残る
- 100万円を超える大口入出金は金融機関から税務署へ自動報告される
- PayPay・LINE Payなどキャッシュレス送金も履歴が残る
- 税務署には 金融機関の入出金や残高を監視する専門部署 があり、不自然な入出金をリアルタイムで把握できる仕組みがある
3. バレる原因②:マイナンバー制度
- 銀行口座とマイナンバーはすでに紐付けされている可能性がある
- 収入や資産の流れを一元的に把握される
- 「誰から誰に渡ったお金か」を追跡する仕組みが整備済みである
4. バレる原因③:住民税通知で発覚
- 会社員で副業を隠している人は、住民税の通知を通じて会社に知られる可能性が高く注意が必要です。
- 扶養に入っている人も、副業収入が増えることで扶養条件から外れてしまい、親や配偶者に通知が届くことがあります。
- パパ活収入を申告しないと税務調査でバレて追徴課税がおき、住民税額が会社に通知がいってバレます
5. バレる原因④:SNSやネット投稿
- 高級バッグの購入や豪華な旅行写真をSNSに投稿すると、税務署がそのアカウントを特定することがあります。
- 税務署にはSNSを専門に監視する部署があり、不自然な消費や収入に関する発信は重点的にチェックされています。
- 実際に「SNSでの自慢投稿」が調査のきっかけとなるケースは少なくなく、日常の発信が思わぬリスクになる可能性があります。
6. バレる原因⑤:第三者からの通報
- 元交際相手やトラブルになったパパ、あるいは嫉妬した友人などからの匿名通報によって、税務署に情報が伝わることがあります。
- 税務署は「確度の高い通報」があった場合には必ず調査に動くため、内部事情を知る人からの指摘は特にリスクが高いです。
- 実際に、このような通報がきっかけとなって調査が始まるケースは少なくありません。
7. バレる原因⑥:生活水準との不一致
- 所得ゼロと申告しているのにブランドバッグを購入したり高級旅行をしていると、申告内容と生活実態が合わず調査対象になる可能性があります。
- 税務署は「生活費と所得のバランス」を重視しており、不自然に見える消費はすぐに疑われます。
- こうした場合には、生活水準から所得を割り出して課税する「推計課税」が行われることもあります。
8. 図解:税金がバレる仕組み
銀行口座・送金アプリ ─┐
├─▶ 税務署データベース ──▶ 収入の不一致を検出
マイナンバー照合 ─┘
住民税通知 ─────────────┐
├─▶ 税務署の専門部署でクロスチェック
SNS投稿監視(専門部署あり) ──┘
第三者通報 ──────▶ 調査開始の引き金
税務調査はこうやって広がる!芋づる式の仕組みを解説
「税務調査はこうやって広がる!芋づる式の仕組みを解説」 では、ひとつの調査がきっかけとなり、関係者や取引先へと次々と調査が広がっていく「芋づる式」の仕組みを分かりやすく解説しています。
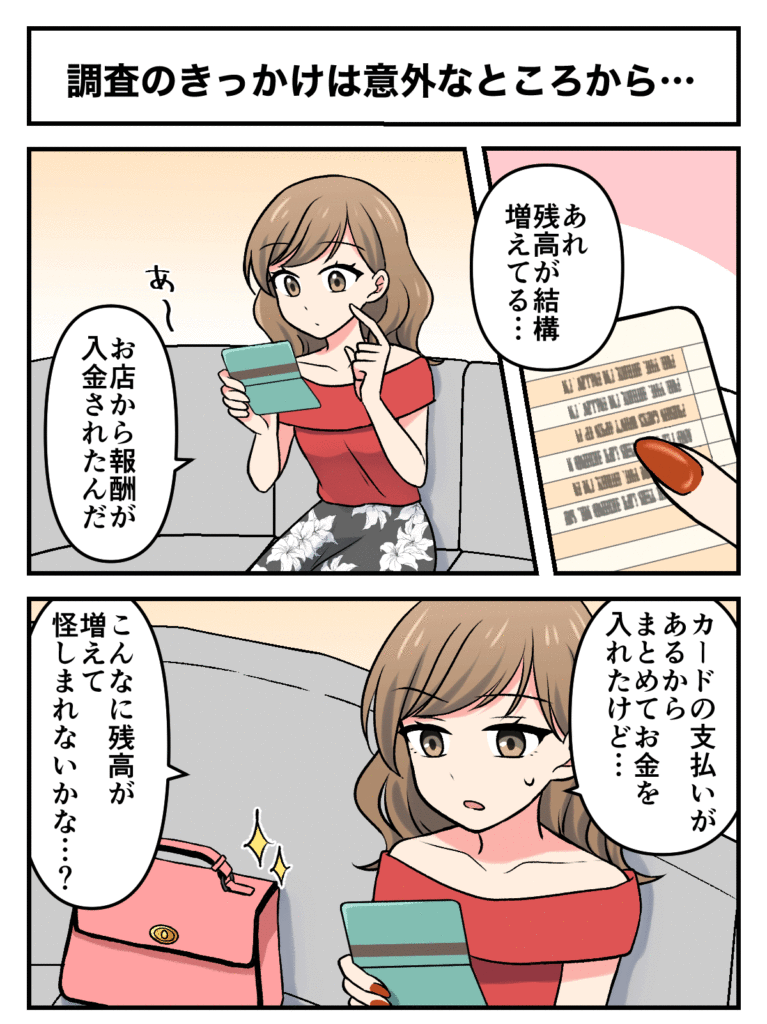
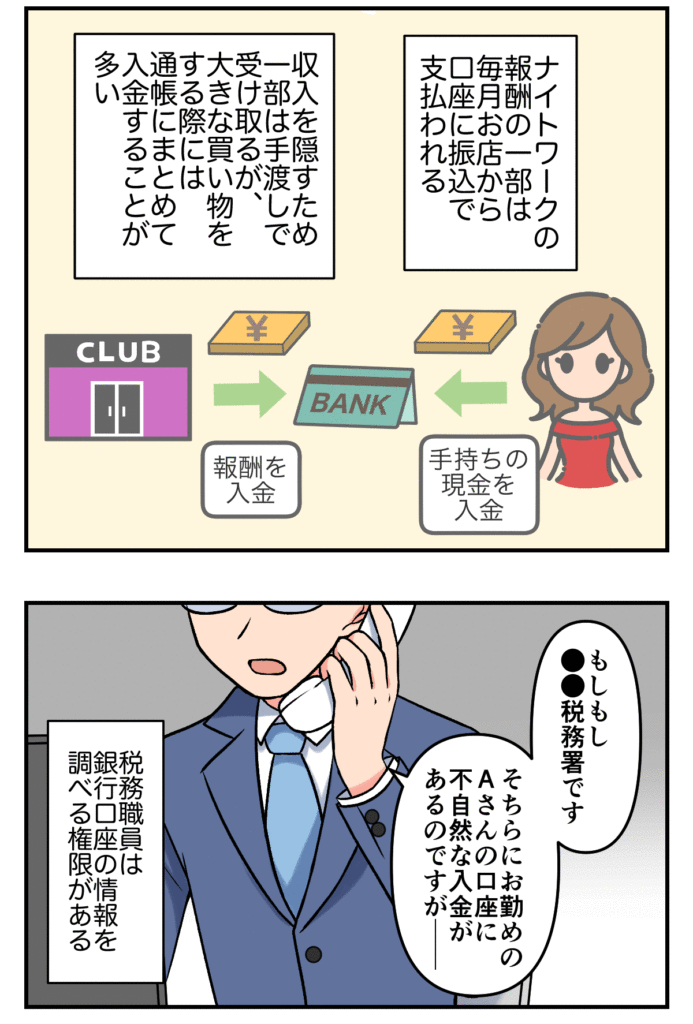
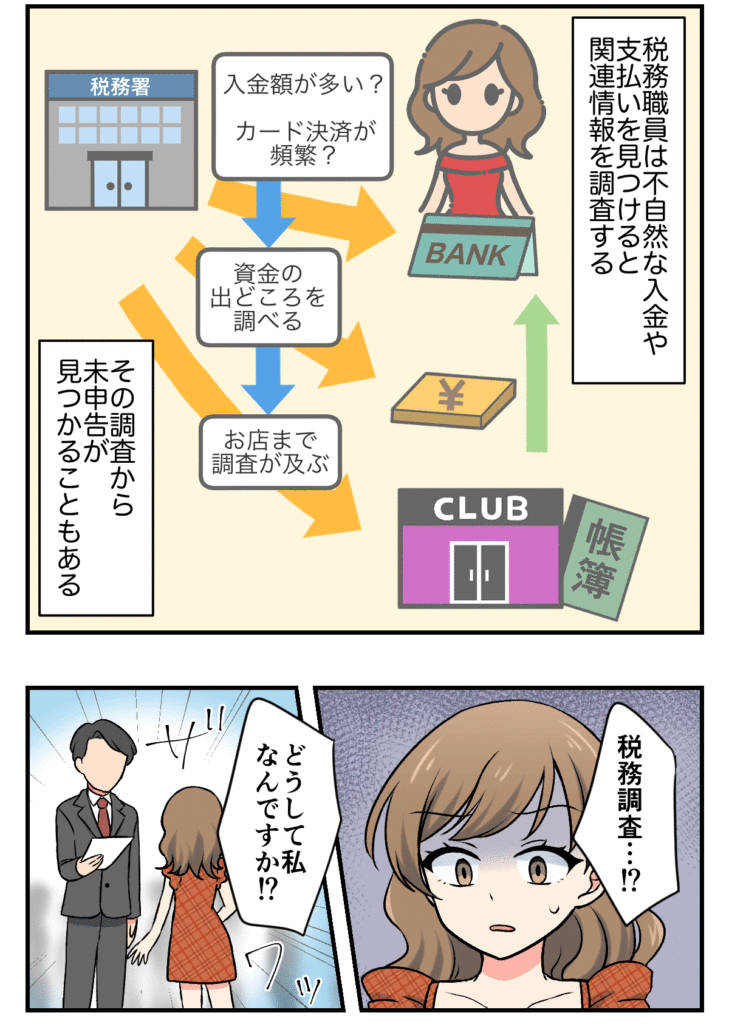
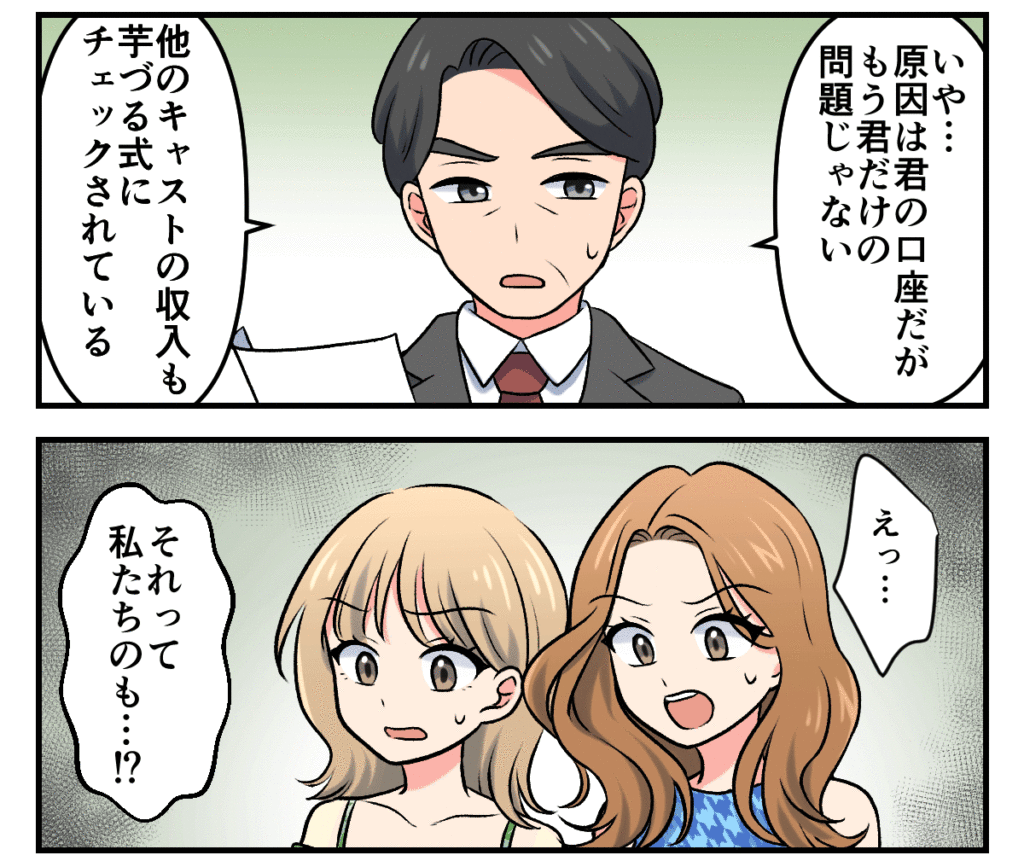
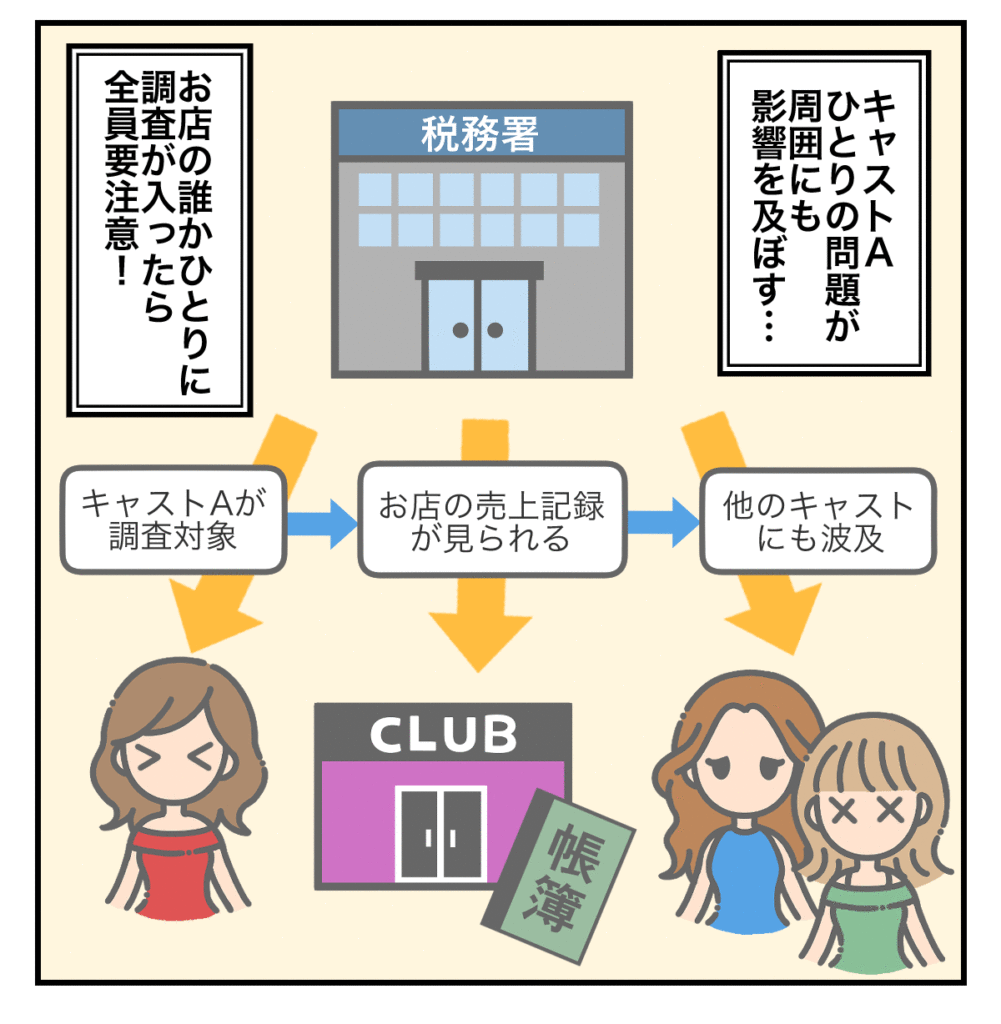
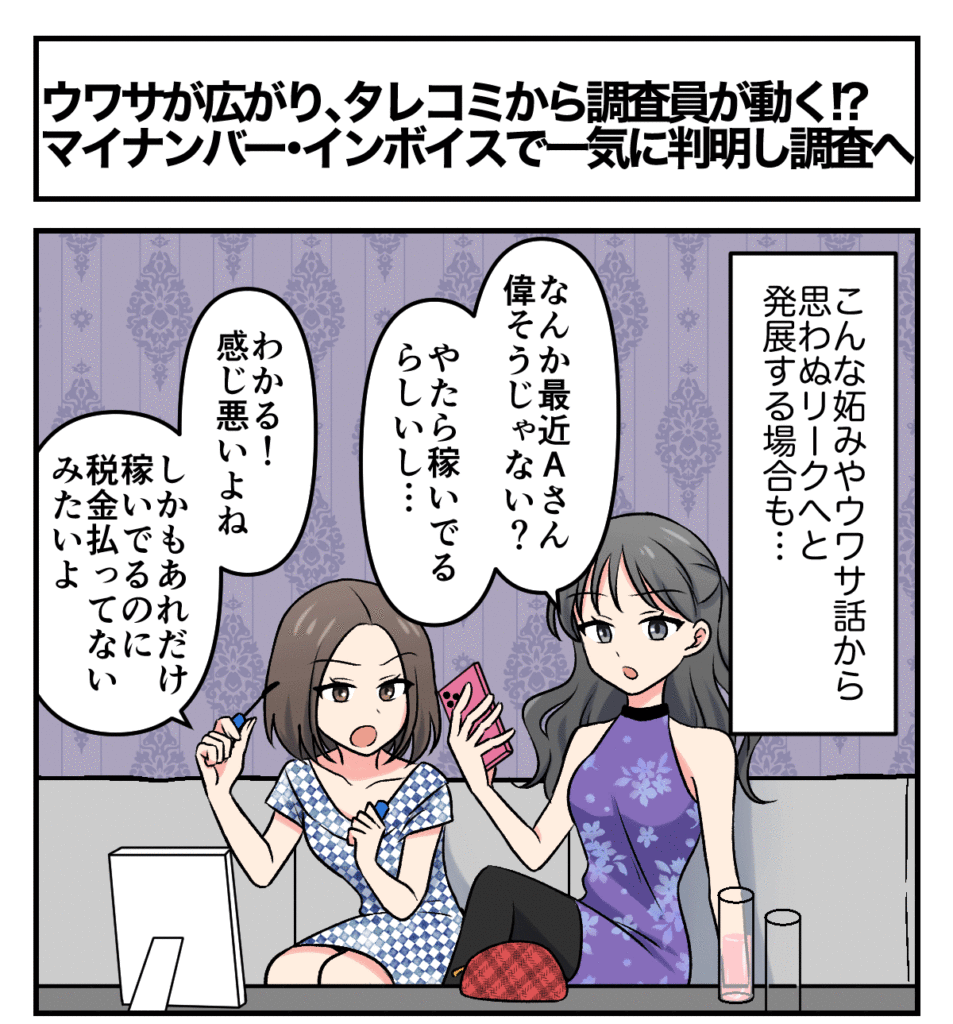
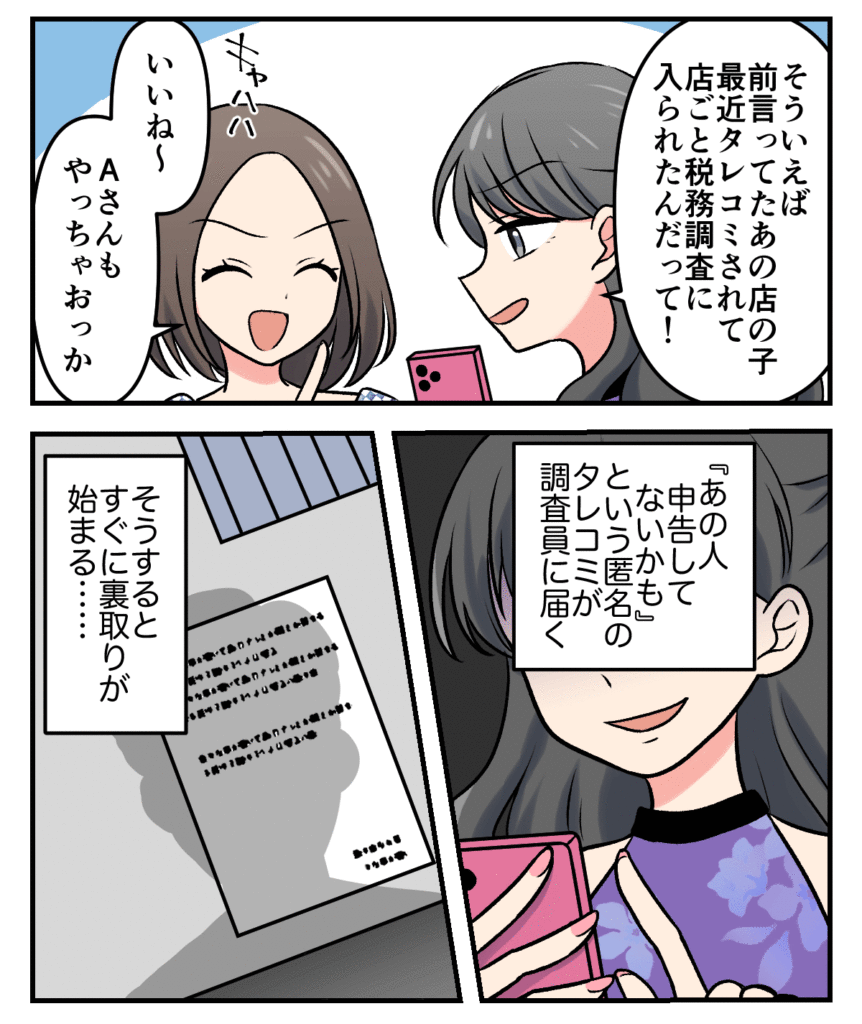
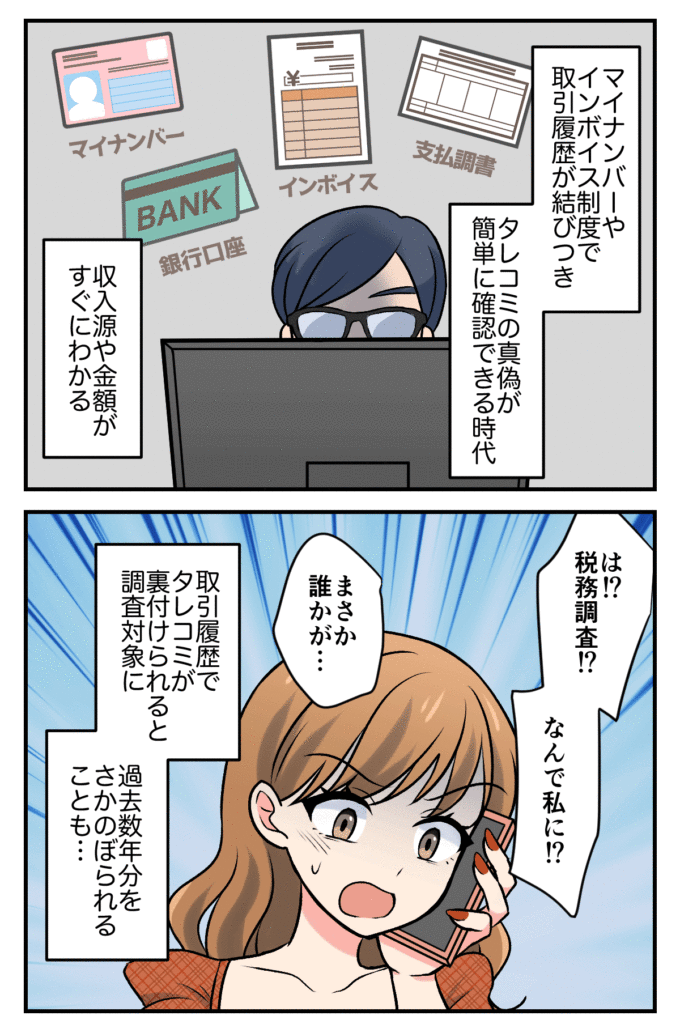
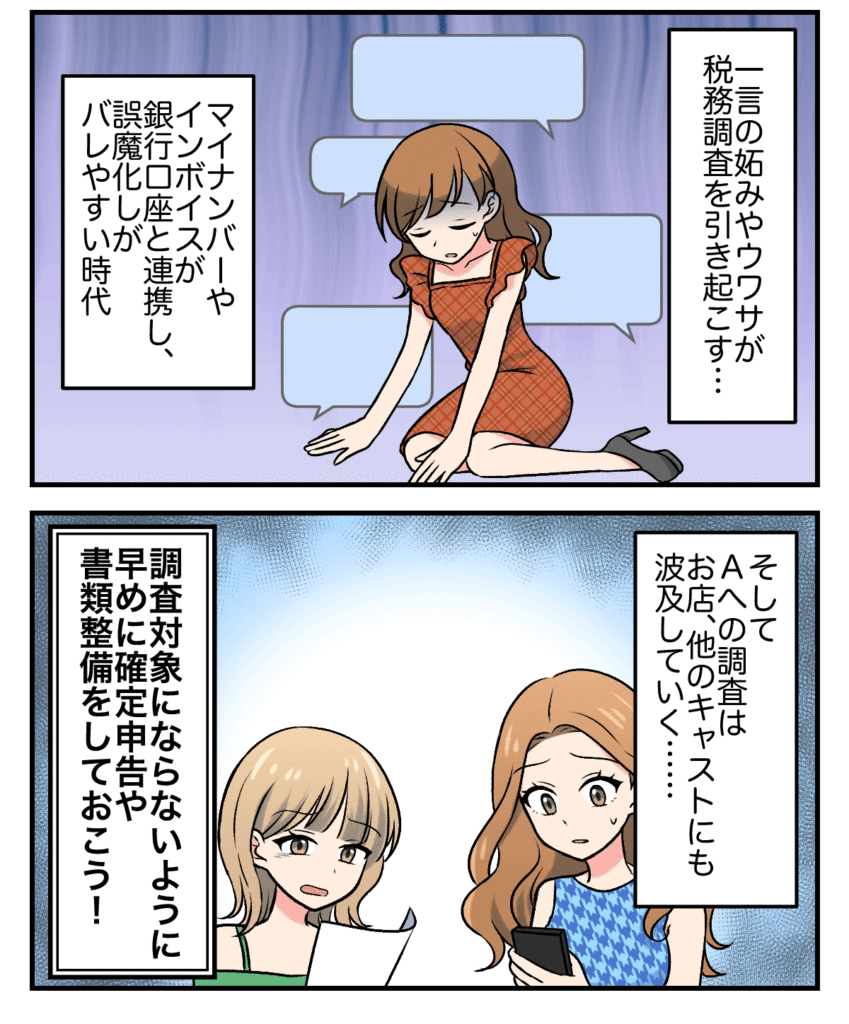
さらにこの続きを見たい場合は、LINE登録してリッチメニューから確認してください!
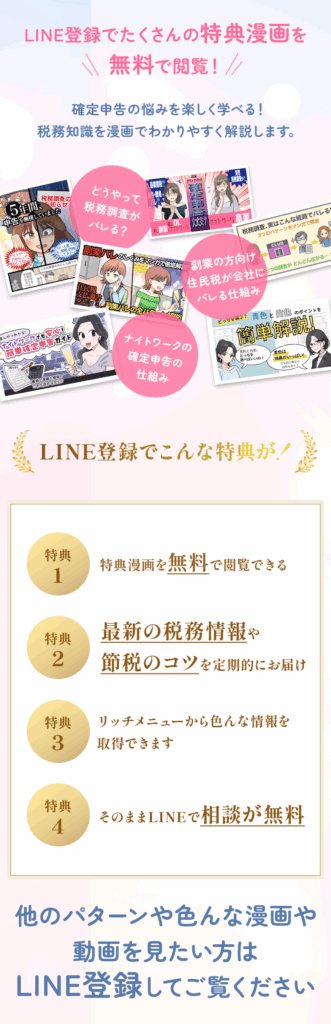
あわせて読みたい
9. 実際にバレた事例
事例A:銀行口座の入金でバレた
A子さんは毎月20万円、年間240万円をパパから振り込んでもらっていました。
「振込名義を変えてもらえばバレない」と考えていましたが、金融機関の大口入出金情報は税務署に自動的に報告されます。
事例B:住民税で会社にバレた
会社員のB子さんは、扶養に入りながら副業でパパ活をしていました。
しかし、住民税の通知が会社経由で届いた際に、金額が通常より大きくなっていることに経理担当が気付き、会社へ報告。
事例C:SNSの投稿と通報でバレた
C子さんは毎月のようにインスタに高級ブランドバッグや海外旅行の写真をアップ。
「フォロワーだから大丈夫」と思っていましたが、SNSには税務署が監視する専門部署があります。
また、知人や元交際相手が嫉妬やトラブルから匿名で税務署に通報することもあります。
実際に、国税庁は公式に 「課税・徴収漏れに関する情報提供フォーム」 を公開しており、誰でもネットから簡単に通報できます。
👉 国税庁 情報提供フォームはこちら
C子さんのケースでも、SNSでの派手な生活ぶりを見た知人がこのフォームから通報。
税務署はその情報をもとに通帳履歴とSNS投稿を突き合わせ、実際の調査に発展。
事例D:匿名タレコミから発覚
D子さんは「手渡しでもらえば絶対にバレない」と思っていましたが、同業キャスト仲間との金銭トラブルで口論になり、相手が税務署に匿名で通報。
税務署は「信憑性の高い通報」に基づき調査を開始。
このように「銀行口座」「住民税」「SNS」「通報」など、バレるルートは複数あります。
そして税務署は 金融機関データ・SNS発信・通報情報を突き合わせることで、無申告を簡単に見抜く仕組みを持っています。
10. 無申告リスク
無申告をすると本税だけでなく、さまざまなペナルティが加算され、負担は一気に大きくなります。代表的なものは以下の通りです。
- 無申告加算税:15〜20%
- 延滞税:最大14.6%
- 重加算税:35〜40%
これらを合算すると、本税が100万円の場合でも70万円以上の追加課税となる可能性があります。
さらに金銭的な負担だけでなく、「親や会社にバレる」という社会的リスクも大きく、信用や人間関係を損なう危険性があります。
あわせて読みたい
11. 対策:安心して活動するために
収入は必ず記録しておきましょう。
通帳への入金履歴や送金アプリの明細、またはノートに書き残すだけでも構い、証拠を残すことで後から安心できます。
贈与か所得か迷ったときは税理士に相談しましょう。
自分だけで判断すると誤りやすく、追徴課税につながる恐れがあるため、専門家に確認するのが安全です。
早めに修正申告をするとメリットがあります。
税務署に指摘される前に自分から申告し直すことで、重加算税などの重いペナルティを避けられる可能性があります。
「バレないだろう」ではなく「正しく申告して安心する」ことを選びましょう。
短期的にごまかしても後から発覚すれば負担は大きくなりますが、正しく申告しておけば将来にわたって安心して生活できます。
まとめ
- パパ活による収入は、複数のルートから必ず把握されます。
- 税務署には、SNSを監視する専門部署と、金融機関の入出金を監視する専門部署が存在いたします。
- 無申告は税金面のリスクにとどまらず、人間関係や社会的な立場までも危うくします。
- パパ活をしている皆様へ──安心して活動を続けていただくためにも、必ず正しい申告と適切な管理を心がけましょう。
FAQ(よくある質問10選)
- パパ活でもらったお金は本当にバレますか?
はい。銀行口座・マイナンバー・SNSなど複数ルートから把握されます。
- 手渡しでもらったら大丈夫?
生活水準と収入の不一致から推計課税されることがあります。
- 年間100万円程度なら問題ない?
贈与税や所得税の申告義務が発生する可能性があります。
- 会社や家族にバレるきっかけは?
住民税通知での不一致が典型的です。
あわせて読みたい
- SNSに投稿しなければ安心?
銀行や送金アプリの履歴から十分に発覚します。
- 複数のパパからもらった場合は?
合算して判定されます。1人ごとに110万円非課税ではありません。
- 過去の未申告はどうすれば?
修正申告をすれば加算税が軽減される可能性があります。
- 税務署にはSNSを監視する部署があるの?
はい。ネット発信も調査対象になります。
- 金融機関の残高まで監視される?
はい。専門部署でデータが分析されています。
- 税理士に相談したら情報は漏れない?
税理士には守秘義務があるため安心して相談できます。
記事監修者の略歴
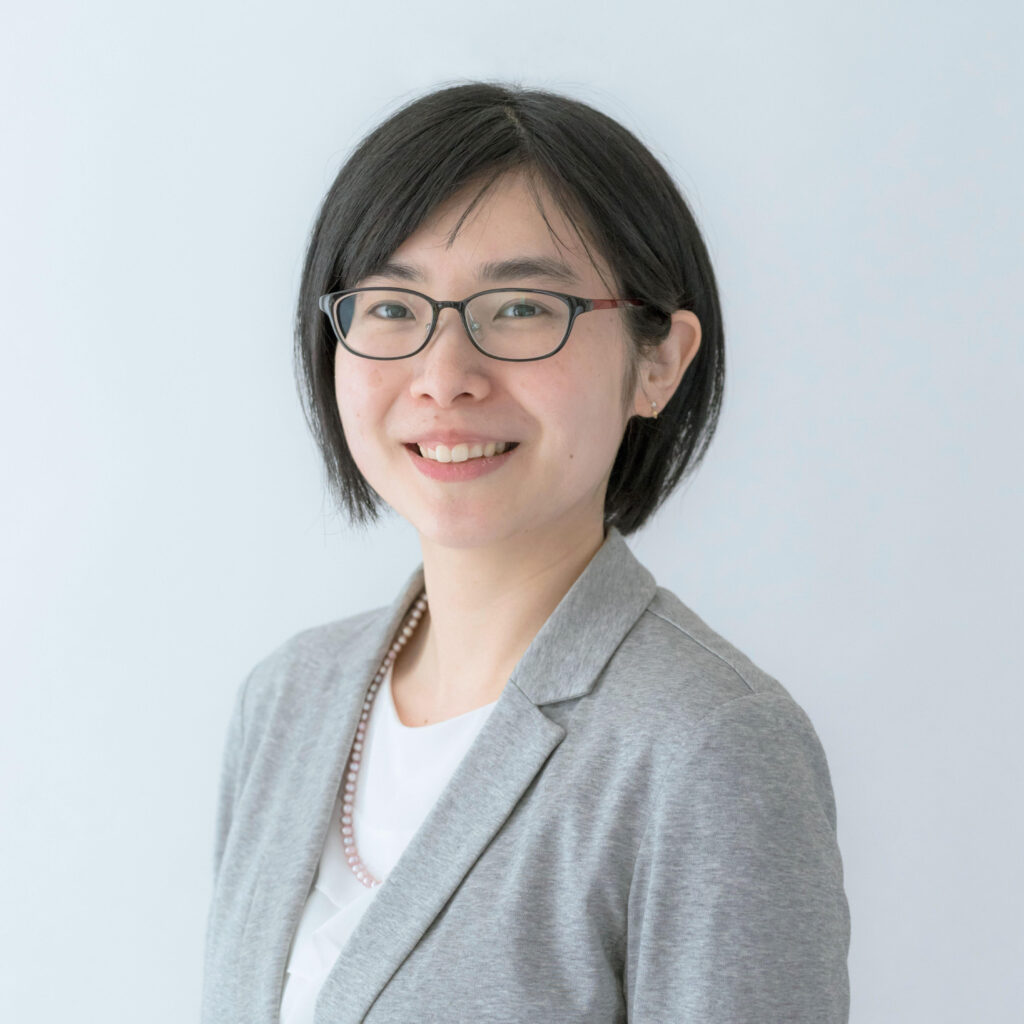
記事監修者
内山智絵 公認会計士・税理士
略歴
新潟大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。
監査法人で約10年勤務後、出産・育児を機に独立。
現在は3児の母として子育てをしながら、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
内山会計事務所 https://uchiyama-kaikei.com/